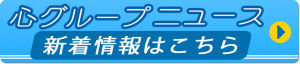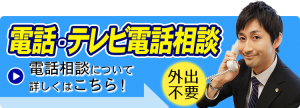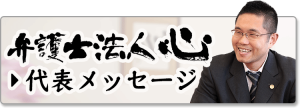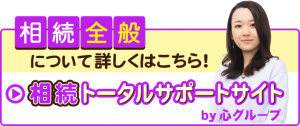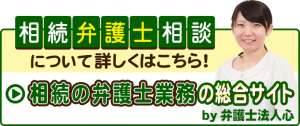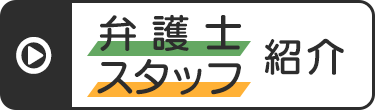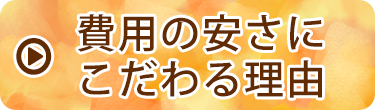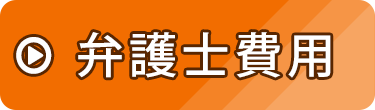相続放棄したかどうかについて確認する方法
1 家庭裁判所に相続放棄をしたか問い合わせをする
相続放棄は、家庭裁判所で行う手続なので、「ある人について、相続放棄がなされたかどうか」は、家庭裁判所の記録に残っています。
そのため、相続人が相続放棄したかどうかを知りたい場合は、家庭裁判所へ問い合わせることで確認できます。
ただし、電話で問い合わせをしても、回答はしてくれませんので、書面で回答を求める必要があります。
2 家庭裁判所に提出する書類
相続放棄の有無を確認する場合、家庭裁判所に対し、「照会書」というものを提出します。
「照会書」には、亡くなった人の情報を記載した上で、「この人が相続放棄をしたのかどうか、教えて欲しい」という『この人』の氏名を記載します。
たとえば、「大阪 太郎」という人が亡くなり、相続人の中に、「大阪 次郎」という人がいた場合、「照会書」には、「大阪 太郎さんの相続について、大阪 次郎さんが相続放棄したかどうか教えて欲しい」旨の記載をします。
家庭裁判所は、氏名で同一人物かどうか判断しているため、たとえば「大阪 『二』郎」などと記載した場合には、正確な回答が行われないことがありますので、注意が必要です。
参考リンク:裁判所・家事事件の各種申請で使う書式について
3 どこの家庭裁判所に提出するのか
相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で行います。
そのため、「照会書」の提出も、亡くなった方の最後の住所地を管轄する裁判所に行います。
例えば、亡くなった方の最後の住所地が大阪市であった場合、大阪家庭裁判所に提出することになります。
参考リンク:大阪府内の管轄区域表
亡くなった方の最後の住所地は、住民票(除票)で確認する必要があります。
4 誰でも「照会書」を提出できるわけではない
相続放棄の有無は、プライバシーにかかわることですので、誰でも照会できるわけではありません。
法的に何らかの利害関係を持っている人だけが、照会できます。
たとえば、他の相続人、亡くなっていた方にお金を貸していた人など、一定の利害関係がないと、照会はできません。
5 必要な資料
「照会書」には、必要な資料を添付することになります。
たとえば、亡くなった方の住民票(除票)や、照会をしている方の利害関係を証明する書類などが必要で、どの立場の方が照会をするかによって異なります。
参考リンク:裁判所・相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1‐1‐3
大阪駅前第3ビル30F
(大阪弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク