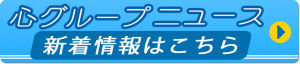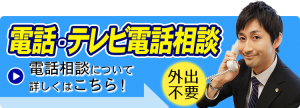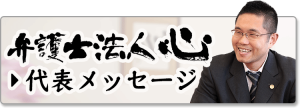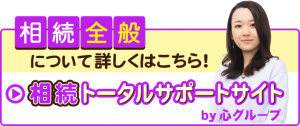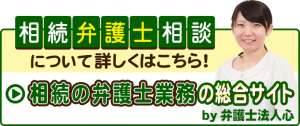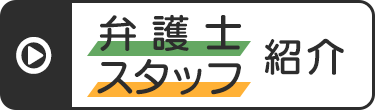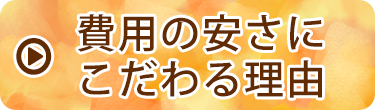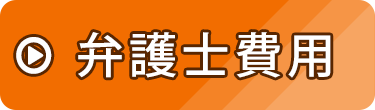相続放棄の申述書の書き方
1 相続放棄の手続きでは申述書を作成する
相続放棄をする場合は、「相続放棄をしたい」という意思を裁判所に伝える必要があります。
そのために提出する書類を「相続放棄の申述書」といいます。
相続放棄の申述書の書式は、裁判所のホームページなどで入手できます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述書(成人)
相続放棄は1回勝負であるため、申述書の書き方で失敗すると、取り返しがつかないかもしれません。
そのため、法的に問題のない申述書を作成する必要があります。
ここでは、相続放棄の申述書の書き方について、ご説明します。
2 相続放棄の当事者について記載する
裁判所にとっては、誰が亡くなって、誰が相続人なのかということは知りようがない事柄です。
そこで、まずは亡くなった方を特定できるだけの情報が必要になります。
具体的には亡くなった方の本籍地、最後の住所、氏名、生年月日などの情報を記載することになります。
次に、相続放棄をする人の情報について記載します。
亡くなった方と同様、本籍地、住所、氏名、生年月日はもちろん、亡くなった方との関係(続柄)も記載します。
3 相続の開始を知った日を記載する
相続放棄は「相続の開始を知った日」から3か月という期限があります。
そのため、いつ相続の開始を知ったのかを記載しなければなりません。
「相続の開始を知る」とは、ご家族が亡くなったことと、自分が相続人になったことの2つの事実を知った時を指します。
すでに亡くなってから3か月が経過している場合は、慎重な記載が必要であるため、相続放棄に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
4 相続放棄の理由を記載する
なぜ相続放棄をするのかについて、その理由を記載します。
たとえば、プラスの財産よりも借金の方が多いからという理由や、他の相続人に遺産を相続して欲しいからという理由が考えられます。
このとき、なんと書こうか迷われる方もいらっしゃるかもしれませんが、相続放棄の理由が原因で、相続放棄が認められなくなるという可能性は低いので、正直な理由を記載すれば問題ありません。
5 遺産の詳細を記載する
どのような遺産があるのかを記載します。
たとえば、不動産の情報や、預貯金に関する情報を記載します。
他方、マイナスの遺産である借金の情報なども記載します。
お役立ち情報
(目次)
- 相続放棄が受理されないケース
- 相続放棄後にしてはいけないこと
- 相続放棄したかどうかについて確認する方法
- 相続放棄はいつまでできるか
- 相続放棄できないケース
- 相続放棄の申述書の書き方
- 相続放棄の理由の書き方
- 相続放棄の期限
- 自分で相続放棄ができるのか
- 被相続人の生前に相続放棄ができるか
- 相続放棄を取り消すことはできるか
- 相続放棄と管理義務
- 相続放棄をした場合に代襲相続は発生するか
- 相続放棄をした場合に死亡保険金はどう扱われるか
- 相続放棄での生命保険の扱い
- 相続放棄と未払の公共料金
- 相続放棄をすると土地はどうなるか
- 相続放棄をしたら墓はどうなるか
- 認知症の方の相続放棄
- 全員が相続放棄をしたら家はどうなるか
- 相続放棄と遺品整理
- 未成年の方の相続放棄
受付時間
平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)
所在地
〒530-0001大阪府大阪市北区
梅田1‐1‐3
大阪駅前第3ビル30F
(大阪弁護士会所属)
0120-41-2403
お役立ちリンク